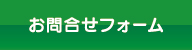2016年05月16日 [Default]
現在の法律では定年年齢は最低でも60歳とするよう求められております。
そして、65歳までの希望者への再雇用や、定年延長が義務付けられております。
これは主に年金支給開始年齢が引き上げられたことに伴う措置です。
この度、某社で定年後に再雇用されたトラック運転手が、「定年前と同じ業務」なのに賃金を下げられたのは違法だとする訴訟の判決があり、裁判所は「業務の内容や責任が同じなのに賃金を下げるのは、労働契約法に反する」として、某社に定年前の賃金規程を適用して差額分を支払うように命じました。
定年に達した社員を、1年ごとの嘱託社員として再雇用する事例は非常に多くあります。
そして大方の企業が賃金に関しては定年前より引き下げて契約しているのではないでしょうか。
問題は、「職務内容」や「責任」等の労働条件が定年前と比較してどうか!?ということになります。
労働契約法20条は、正社員のような無期雇用で働く人と、再雇用など有期雇用で働く人との間で、不合理な差別をすることを禁じております。
判決でも「特段の事情」がない限りは、同じ業務内容にもかかわらず賃金格差を設けることは不合理だと指摘しております。
某社は、「運転手は賃下げに同意していた」と主張しましたが、それも特段の事情には当たらないと退けております。
実際、ある調査では、企業の83・8%が、再雇用者は「定年時点と同じ仕事内容」と答え、賃金は「定年時の68.3%」と答えております。
現時点でも多くの企業が同様の条件のもと嘱託社員として働かせているのではないでしょうか。
今すぐにでも対応を考えなければならない状況に立たされていると言ってよろしいでしょう。
どうすればいいのか?
判決でも求めている「職務内容」「責任」を定年前と比較してどうかを再度チェックしましょう。
他にも、労働時間や労働日数、異動や転勤の有無等、「特段の事情」に当てはまるかどうか再チェックしましょう。
「特段の事情」が無ければ、すぐに対応を考えなければなりません。
今回の判決を受けて、今後も同様の訴えが起きてくる可能性が高まります。
政府も「同一労働同一賃金」に向けて動いている最中です。
お悩みの際には、私ども専門家である社会保険労務士に是非ともご相談ください。
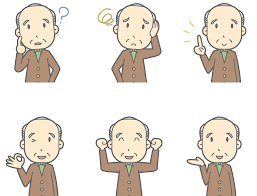
そして、65歳までの希望者への再雇用や、定年延長が義務付けられております。
これは主に年金支給開始年齢が引き上げられたことに伴う措置です。
この度、某社で定年後に再雇用されたトラック運転手が、「定年前と同じ業務」なのに賃金を下げられたのは違法だとする訴訟の判決があり、裁判所は「業務の内容や責任が同じなのに賃金を下げるのは、労働契約法に反する」として、某社に定年前の賃金規程を適用して差額分を支払うように命じました。
定年に達した社員を、1年ごとの嘱託社員として再雇用する事例は非常に多くあります。
そして大方の企業が賃金に関しては定年前より引き下げて契約しているのではないでしょうか。
問題は、「職務内容」や「責任」等の労働条件が定年前と比較してどうか!?ということになります。
労働契約法20条は、正社員のような無期雇用で働く人と、再雇用など有期雇用で働く人との間で、不合理な差別をすることを禁じております。
判決でも「特段の事情」がない限りは、同じ業務内容にもかかわらず賃金格差を設けることは不合理だと指摘しております。
某社は、「運転手は賃下げに同意していた」と主張しましたが、それも特段の事情には当たらないと退けております。
実際、ある調査では、企業の83・8%が、再雇用者は「定年時点と同じ仕事内容」と答え、賃金は「定年時の68.3%」と答えております。
現時点でも多くの企業が同様の条件のもと嘱託社員として働かせているのではないでしょうか。
今すぐにでも対応を考えなければならない状況に立たされていると言ってよろしいでしょう。
どうすればいいのか?
判決でも求めている「職務内容」「責任」を定年前と比較してどうかを再度チェックしましょう。
他にも、労働時間や労働日数、異動や転勤の有無等、「特段の事情」に当てはまるかどうか再チェックしましょう。
「特段の事情」が無ければ、すぐに対応を考えなければなりません。
今回の判決を受けて、今後も同様の訴えが起きてくる可能性が高まります。
政府も「同一労働同一賃金」に向けて動いている最中です。
お悩みの際には、私ども専門家である社会保険労務士に是非ともご相談ください。
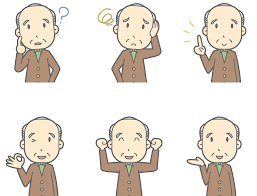
2016年05月09日 [Default]
長いゴールデンウィークが終了しました。
最大で10日間の連休だったとのことです。
10連休もあると嬉しいですが、終わった後は五月病になりそうです・・・。
当事務所はカレンダー通りで稼働しておりましたが、かなり休んだ気分です。
ゴールデンウィークが終わってからこの記事を書くのもおかしな話なのですが、
経営者の皆様は「計画年休」制度をご存知でしょうか?
「計画年休」とは文字通り、計画的に年次有給休暇を消化するための制度です。
運用方法は、まず就業規則に「計画年休」の規定を入れます。
そして、労働者代表者と書面により「計画年休」の労使協定書を作成し協定します。
どのような効果があるかというと、
よく労働者側の意見として、「有給休暇が取りにくい雰囲気がある」「忙しくて取る暇がない」などがあります。
結果として有給休暇を使えず、2年間の時効も経過して使えずじまいに終わってしまう、ということが往々にしてあります。
日本は有給休暇取得率が低いのです。
これを是正しようと、今国も動いている制度でして、
労働者の保持する年次有給休暇のうち、5日間は労働者が自由に使える年次有給休暇として残します。
5日を超える部分の有給休暇に関して、協定を結ぶことにより、使用者が取ってほしい日に有給休暇を充てることが可能になります。
例:年次有給休暇が15日の方は、10日間は使用者が指定する日に有給休暇を使うことが可能になります。
この制度によって有給休暇取得率を労使双方方で上げましょうという制度です。
今回のような、ゴールデンウィーク中に平日がある場合、
使用者が、「取引先も休みで仕事もあまりないから平日に有給休暇を充てましょう」となれば
カレンダー通りの方も10連休が可能になるわけです。
使い方によっては労使双方でとてもメリットのある制度です。
是非ご検討いただければと思います。
ちなみに私は、ゴールデンウィーク最終日は茅ヶ崎海岸で「地引網」に行ってきました。

何十年ぶりかの体験でした。

でっかいヒラメや太刀魚、イカやシラスが大漁でした!

来賓で来ていた元Jリーガーのカレン・ロバートさんと記念撮影しました
最大で10日間の連休だったとのことです。
10連休もあると嬉しいですが、終わった後は五月病になりそうです・・・。
当事務所はカレンダー通りで稼働しておりましたが、かなり休んだ気分です。
ゴールデンウィークが終わってからこの記事を書くのもおかしな話なのですが、
経営者の皆様は「計画年休」制度をご存知でしょうか?
「計画年休」とは文字通り、計画的に年次有給休暇を消化するための制度です。
運用方法は、まず就業規則に「計画年休」の規定を入れます。
そして、労働者代表者と書面により「計画年休」の労使協定書を作成し協定します。
どのような効果があるかというと、
よく労働者側の意見として、「有給休暇が取りにくい雰囲気がある」「忙しくて取る暇がない」などがあります。
結果として有給休暇を使えず、2年間の時効も経過して使えずじまいに終わってしまう、ということが往々にしてあります。
日本は有給休暇取得率が低いのです。
これを是正しようと、今国も動いている制度でして、
労働者の保持する年次有給休暇のうち、5日間は労働者が自由に使える年次有給休暇として残します。
5日を超える部分の有給休暇に関して、協定を結ぶことにより、使用者が取ってほしい日に有給休暇を充てることが可能になります。
例:年次有給休暇が15日の方は、10日間は使用者が指定する日に有給休暇を使うことが可能になります。
この制度によって有給休暇取得率を労使双方方で上げましょうという制度です。
今回のような、ゴールデンウィーク中に平日がある場合、
使用者が、「取引先も休みで仕事もあまりないから平日に有給休暇を充てましょう」となれば
カレンダー通りの方も10連休が可能になるわけです。
使い方によっては労使双方でとてもメリットのある制度です。
是非ご検討いただければと思います。
ちなみに私は、ゴールデンウィーク最終日は茅ヶ崎海岸で「地引網」に行ってきました。

何十年ぶりかの体験でした。

でっかいヒラメや太刀魚、イカやシラスが大漁でした!

来賓で来ていた元Jリーガーのカレン・ロバートさんと記念撮影しました
2016年05月06日 [Default]
労災は労働中にとどまらず、通勤途中や家に帰るまでの退勤途上においても該当します。
そして、この通勤退勤途中の労災においても一定の経営者責任が問われる場合があります。
よって、経営者はアルバイト等も含めた社員全員を十分に管理しておく必要があるのです。
某社の男性が自殺したのは長時間労働が原因だとした訴えの判決がありました。
内容は、男性はある日会社で深夜まで勤務した後の帰宅中に交通事故を起こしてしまったそうです。
交通事故を起こした男性もけがで次の日以降出勤できなくなったそうです。
そして翌月に自殺したということ。
調べると、交通事故前1ヶ月の時間外労働は177時間だったとのこと。
判決では、労務管理の責任者であった経営者が「出勤簿も確認せず、労働時間の管理などを怠った」と指摘し損害賠償支払いを命じました。
経営者は大変だと思います。
経営責任も人の管理責任も問われたらたまりません。
しかし、責任は経営者に降りかかってきます。
どうしたらいいのか?
経営者自らが管理できないのであれば、経営者から下の部課長クラスにしっかりと「ヒト」の管理をするよう強く指示することです。
強く指示といって、下の部課長クラスがストレスを抱えてしまっては意味がないので重要性を認識させることです。
日々の出退勤の管理、残業時間の管理は最低でもしておかなければなりません。
上記の判例では、事故前1ヶ月の残業時間が177時間となっておりましたが、一般に月の残業時間が100時間を超えると過労死の危険性が増すと指摘されており、また3ヶ月平均80時間超の残業時間でも同様の危険性が指摘されております。
ちなみに「社員が勝手に残業していた」、「命令していない」はほぼ通用しないと考えてください。
「黙示の命令」があったとみなされるのがほとんどです。
残業時間を極力減らし、仕事の効率性をあげ、一人一人がコストパフォーマンスを上げれば結果はついてくると思います。
会社としては残業代のコストが減り、こういった労務リスクが減り、経営も安定すれば最高だと思います。
従業員としても残業が減れば、残業代は少なくなるかもしれませんが、ワーク・ライフ・バランスを実現できます。
当事務所も、残業時間の多いお客様の相談に多く乗っております。
何か起きてからでは遅いのです。
ご連絡いただければお客様の立場に立って最善のアドバイスをさせていただきます。

そして、この通勤退勤途中の労災においても一定の経営者責任が問われる場合があります。
よって、経営者はアルバイト等も含めた社員全員を十分に管理しておく必要があるのです。
某社の男性が自殺したのは長時間労働が原因だとした訴えの判決がありました。
内容は、男性はある日会社で深夜まで勤務した後の帰宅中に交通事故を起こしてしまったそうです。
交通事故を起こした男性もけがで次の日以降出勤できなくなったそうです。
そして翌月に自殺したということ。
調べると、交通事故前1ヶ月の時間外労働は177時間だったとのこと。
判決では、労務管理の責任者であった経営者が「出勤簿も確認せず、労働時間の管理などを怠った」と指摘し損害賠償支払いを命じました。
経営者は大変だと思います。
経営責任も人の管理責任も問われたらたまりません。
しかし、責任は経営者に降りかかってきます。
どうしたらいいのか?
経営者自らが管理できないのであれば、経営者から下の部課長クラスにしっかりと「ヒト」の管理をするよう強く指示することです。
強く指示といって、下の部課長クラスがストレスを抱えてしまっては意味がないので重要性を認識させることです。
日々の出退勤の管理、残業時間の管理は最低でもしておかなければなりません。
上記の判例では、事故前1ヶ月の残業時間が177時間となっておりましたが、一般に月の残業時間が100時間を超えると過労死の危険性が増すと指摘されており、また3ヶ月平均80時間超の残業時間でも同様の危険性が指摘されております。
ちなみに「社員が勝手に残業していた」、「命令していない」はほぼ通用しないと考えてください。
「黙示の命令」があったとみなされるのがほとんどです。
残業時間を極力減らし、仕事の効率性をあげ、一人一人がコストパフォーマンスを上げれば結果はついてくると思います。
会社としては残業代のコストが減り、こういった労務リスクが減り、経営も安定すれば最高だと思います。
従業員としても残業が減れば、残業代は少なくなるかもしれませんが、ワーク・ライフ・バランスを実現できます。
当事務所も、残業時間の多いお客様の相談に多く乗っております。
何か起きてからでは遅いのです。
ご連絡いただければお客様の立場に立って最善のアドバイスをさせていただきます。