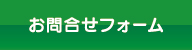2017年11月24日 [Default]
「夢の国」と言えば東京ディズニーランドですよね!
私も今までに10回ぐらい行ったことがあります。
基本的にはいきたくない派です・・・。
遠い(電車でも車でも微妙に・・・)、混雑、並ぶ・・・私ダメです・・・。
それでも若かりし頃友達と行ったり、彼女と行ったり、最近では家族で行ったりしてます。
女性は好きですからね。
基本的に行きたくないのですが、いざ行ってみると楽しい!
パレードとか見てると時間を忘れます。
そこが「夢の国」たる所以なのでしょうか?
さて、そんな東京ディズニーランドの一つの楽しみといえばディズニーキャラクターですよね。
園内で偶然遭遇したときは追っかけて、一緒に写真を撮って・・・。
そして、パレードの主役もディズニーキャラクターたちが楽しそうに踊って、手を振って・・・などですよね。
ただ、冷静に考えるとディズニーキャラクターを演じているのは「従業員」です。
よく「ちっちゃなおっさんが入ってるんじゃないか!?」なんて言ってましたが・・・(苦笑)
大体、小柄な女性が演じているのではないかと推測します。

キャラクターによっても重さや暑さは違うでしょう。
頭には重い被り物をかぶって、首から下も大体着ぐるみで覆われているわけです。
夢の国のキャラクターを演じるのも「過酷な労働」だと考えます。
前置きが長くなりましたが、その東京ディズニーランドで勤務する契約社員の女性に労災認定が下りました。
理由は、着ぐるみを着てショーやパレードに出演していたが、契約から1年9ヶ月ほど経ったころから左腕が重く感じ、手の震えが止まらなくなったが、休みを取りにくいため出演を続けた結果症状が悪化し、左腕を上げると激痛が走り、左手を握っても感覚がなくなってしまうまでに症状が悪化したというのです。
病院で調べたところ、神経や血流の障害で痛みが出る「胸郭出口症候群」という診断が下ったとのことです。
当然治療のため休職し、症状は改善しつつあるが完治はしていないとのこと。
それでも女性は、業務量を減らしての復職を求めているそうです。
このような話をすれば、当然労災だろうと考えられますが、労災認定されるには業務との相当な因果関係が問われます。
今回のようにキャラクターを演じる従業員が負傷等以外で労災認定されるのは珍しいようです。
労災認定された経緯は以下の理由です。
① 発症前後のパレードへの出演回数は計50回にのぼる
② その中で、クリスマスパレードの衣装は首の動きが制限され、重さが10キロ近くあった
③ 更に、その衣装を着て、1回45分のパレードの間、両手を顔より上にあげているように指示されていた
④ 休職になるまでの間の出演期間中に20〜30キロの衣装を着ることもあった
上記を総合して勘案した結果、首から肩、腕にかけて負荷がかかる業務に継続的に従事したことが発症の原因と認められました。
今後、東京ディズニーランドとしては当然同様のことが起きる可能性があることが分かったことですから、十分注意して従業員管理を行っていくことでしょう。
みんなが楽しみにしているディズニーランドのキャラクターが着ぐるみの中では「しんどい顔をして対応をしてる」のでは残念ですよね。
キャラクターを演じる従業員も楽しく、笑顔で働ける環境を整えていただければと思います。
皆様もディズニーランドに行く際には、キャラクターに無理な行動をさせないように、そしてお子様を連れていく際には叩いたりしないように配慮しなければいけませんね(笑)
私も今までに10回ぐらい行ったことがあります。
基本的にはいきたくない派です・・・。
遠い(電車でも車でも微妙に・・・)、混雑、並ぶ・・・私ダメです・・・。
それでも若かりし頃友達と行ったり、彼女と行ったり、最近では家族で行ったりしてます。
女性は好きですからね。
基本的に行きたくないのですが、いざ行ってみると楽しい!
パレードとか見てると時間を忘れます。
そこが「夢の国」たる所以なのでしょうか?
さて、そんな東京ディズニーランドの一つの楽しみといえばディズニーキャラクターですよね。
園内で偶然遭遇したときは追っかけて、一緒に写真を撮って・・・。
そして、パレードの主役もディズニーキャラクターたちが楽しそうに踊って、手を振って・・・などですよね。
ただ、冷静に考えるとディズニーキャラクターを演じているのは「従業員」です。
よく「ちっちゃなおっさんが入ってるんじゃないか!?」なんて言ってましたが・・・(苦笑)
大体、小柄な女性が演じているのではないかと推測します。

キャラクターによっても重さや暑さは違うでしょう。
頭には重い被り物をかぶって、首から下も大体着ぐるみで覆われているわけです。
夢の国のキャラクターを演じるのも「過酷な労働」だと考えます。
前置きが長くなりましたが、その東京ディズニーランドで勤務する契約社員の女性に労災認定が下りました。
理由は、着ぐるみを着てショーやパレードに出演していたが、契約から1年9ヶ月ほど経ったころから左腕が重く感じ、手の震えが止まらなくなったが、休みを取りにくいため出演を続けた結果症状が悪化し、左腕を上げると激痛が走り、左手を握っても感覚がなくなってしまうまでに症状が悪化したというのです。
病院で調べたところ、神経や血流の障害で痛みが出る「胸郭出口症候群」という診断が下ったとのことです。
当然治療のため休職し、症状は改善しつつあるが完治はしていないとのこと。
それでも女性は、業務量を減らしての復職を求めているそうです。
このような話をすれば、当然労災だろうと考えられますが、労災認定されるには業務との相当な因果関係が問われます。
今回のようにキャラクターを演じる従業員が負傷等以外で労災認定されるのは珍しいようです。
労災認定された経緯は以下の理由です。
① 発症前後のパレードへの出演回数は計50回にのぼる
② その中で、クリスマスパレードの衣装は首の動きが制限され、重さが10キロ近くあった
③ 更に、その衣装を着て、1回45分のパレードの間、両手を顔より上にあげているように指示されていた
④ 休職になるまでの間の出演期間中に20〜30キロの衣装を着ることもあった
上記を総合して勘案した結果、首から肩、腕にかけて負荷がかかる業務に継続的に従事したことが発症の原因と認められました。
今後、東京ディズニーランドとしては当然同様のことが起きる可能性があることが分かったことですから、十分注意して従業員管理を行っていくことでしょう。
みんなが楽しみにしているディズニーランドのキャラクターが着ぐるみの中では「しんどい顔をして対応をしてる」のでは残念ですよね。
キャラクターを演じる従業員も楽しく、笑顔で働ける環境を整えていただければと思います。
皆様もディズニーランドに行く際には、キャラクターに無理な行動をさせないように、そしてお子様を連れていく際には叩いたりしないように配慮しなければいけませんね(笑)
2017年11月22日 [Default]
兼業・・・その名の通り、「業務を兼ねる」ということですね。
企業で働く従業員が、別の企業でも働くことになります。
副業も意味や内容は違いますが、企業に与える影響については同様に考えて良いと思います。
一般的にこの兼業・副業について就業規則等で企業は禁止しています。
いわゆる「懲戒事由」や「服務規律」項目で明記している企業が多いでしょう。
何故かというと理由はいろいろです。
① 本業(いわゆる主とする企業の)がおろそかになる可能性がある
② 情報漏えいリスクがある
③ 労働時間の管理や健康管理の範囲が曖昧になる
などなどいろいろな問題が考えられます。
当事務所が作成代行する就業規則にも大体こちらの規定は載せております。
当然、お客様も望んでのことです。
そして、この「兼業」が発覚して、結果退職になった従業員もおります。
そんな「兼業・副業」を厚生労働省は、今後逆に普及させていく方向性を示しました!
更に、厚生労働省が就業規則の作成の参考にと案内している「モデル就業規則」の条文も見直し、兼業や副業禁止する項目を削除し、原則として容認する内容に変更する方針だというのです!
?????????????????????
あ〜、またよくわからない、あまりに唐突なことを言っている・・・というのが私の実感です。
国が進めるいわゆる「働き方改革」に沿った流れで、その中で「テレワーク」等を進めていることは理解できます。
「テレワーク」をできる業務内容で、しっかりとした管理が導入企業としてできれば進めていくのは望ましいと思います。
しかし、「テレワークで兼業・副業をやれ」とは言っておらず、あくまで主たる企業の業務を「テレワーク」を使って、ということです。
何故、「兼業」「副業」を推し進めようとしているのか?
国の考えでは、「働き方改革」の一環として、多様な働き方を推進したいということなのかなと思われます。
従業員としてはどうか?
例えば、主とする企業で1日8時間働き、その後別企業で3時間ぐらい働く・・・。
あるいは、主とする企業で月曜日から金曜日まで働き、土日は別企業で働く・・・。
単純に収入が増えるということでしょうか。
よく言えば、主とする企業とは別の職種を兼業先で行い、スキルアップを図るということでしょうか。
企業としてはどうか?
上記のような働き方を従業員に認めても何のメリットも無いような気がします・・・。
「兼業・副業」を認めてくれれば、それを望む従業員にとってはありがたい企業ということにはなるでしょうが・・・。
一貫して言えることは、国として推進するのはいいが様々な事態をしっかり想定しての事か、ということです!
例えば、「兼業・副業」を従業員がした結果、その日の労働時間は当然長くなることが想定されます。
そのような状態での勤務が続いた結果、過重労働による健康疾患や精神疾患を患う。
容易に想定できますよね。
誰が責任を負うんでしょう?
従業員?⇒「だって兼業・副業は認められているし、お金がなくて生活に困っていてどうしようもなかった」
主たる企業?⇒「うちは法定労働時間内で働かせていて、その後の行動まで管理してないよ」
兼業・副業先企業?⇒「従業員が望んだ形で法定労働時間内で契約を結んで働かせているからうちは関係ない」

まあ、このようなことが確実に起きるでしょう・・・。
と言っても、私が思うに国にとっては「想定外」なのかもしれません・・・(苦笑)
とりあえず国が責任を負ってくれるのでしょうか・・・。
前にも述べたように、大方兼業や副業をしたい方は、生活費を補うために「やむを得ず」行うものと考えます。
結果、弱い者に無理をさせることにならないか?
結果、国が掲げる「ワークライフバランス」の実現と逆行することにならないか?
結果、健康を害し、主たる企業でさえも働くことができなくなる事態にはならないか?
まだまだ方針の段階です。
今からでもより深い議論を積み上げて、もっと誰もが納得できる指針を示してもらいたいと思います。
企業で働く従業員が、別の企業でも働くことになります。
副業も意味や内容は違いますが、企業に与える影響については同様に考えて良いと思います。
一般的にこの兼業・副業について就業規則等で企業は禁止しています。
いわゆる「懲戒事由」や「服務規律」項目で明記している企業が多いでしょう。
何故かというと理由はいろいろです。
① 本業(いわゆる主とする企業の)がおろそかになる可能性がある
② 情報漏えいリスクがある
③ 労働時間の管理や健康管理の範囲が曖昧になる
などなどいろいろな問題が考えられます。
当事務所が作成代行する就業規則にも大体こちらの規定は載せております。
当然、お客様も望んでのことです。
そして、この「兼業」が発覚して、結果退職になった従業員もおります。
そんな「兼業・副業」を厚生労働省は、今後逆に普及させていく方向性を示しました!
更に、厚生労働省が就業規則の作成の参考にと案内している「モデル就業規則」の条文も見直し、兼業や副業禁止する項目を削除し、原則として容認する内容に変更する方針だというのです!
?????????????????????
あ〜、またよくわからない、あまりに唐突なことを言っている・・・というのが私の実感です。
国が進めるいわゆる「働き方改革」に沿った流れで、その中で「テレワーク」等を進めていることは理解できます。
「テレワーク」をできる業務内容で、しっかりとした管理が導入企業としてできれば進めていくのは望ましいと思います。
しかし、「テレワークで兼業・副業をやれ」とは言っておらず、あくまで主たる企業の業務を「テレワーク」を使って、ということです。
何故、「兼業」「副業」を推し進めようとしているのか?
国の考えでは、「働き方改革」の一環として、多様な働き方を推進したいということなのかなと思われます。
従業員としてはどうか?
例えば、主とする企業で1日8時間働き、その後別企業で3時間ぐらい働く・・・。
あるいは、主とする企業で月曜日から金曜日まで働き、土日は別企業で働く・・・。
単純に収入が増えるということでしょうか。
よく言えば、主とする企業とは別の職種を兼業先で行い、スキルアップを図るということでしょうか。
企業としてはどうか?
上記のような働き方を従業員に認めても何のメリットも無いような気がします・・・。
「兼業・副業」を認めてくれれば、それを望む従業員にとってはありがたい企業ということにはなるでしょうが・・・。
一貫して言えることは、国として推進するのはいいが様々な事態をしっかり想定しての事か、ということです!
例えば、「兼業・副業」を従業員がした結果、その日の労働時間は当然長くなることが想定されます。
そのような状態での勤務が続いた結果、過重労働による健康疾患や精神疾患を患う。
容易に想定できますよね。
誰が責任を負うんでしょう?
従業員?⇒「だって兼業・副業は認められているし、お金がなくて生活に困っていてどうしようもなかった」
主たる企業?⇒「うちは法定労働時間内で働かせていて、その後の行動まで管理してないよ」
兼業・副業先企業?⇒「従業員が望んだ形で法定労働時間内で契約を結んで働かせているからうちは関係ない」

まあ、このようなことが確実に起きるでしょう・・・。
と言っても、私が思うに国にとっては「想定外」なのかもしれません・・・(苦笑)
とりあえず国が責任を負ってくれるのでしょうか・・・。
前にも述べたように、大方兼業や副業をしたい方は、生活費を補うために「やむを得ず」行うものと考えます。
結果、弱い者に無理をさせることにならないか?
結果、国が掲げる「ワークライフバランス」の実現と逆行することにならないか?
結果、健康を害し、主たる企業でさえも働くことができなくなる事態にはならないか?
まだまだ方針の段階です。
今からでもより深い議論を積み上げて、もっと誰もが納得できる指針を示してもらいたいと思います。
2017年11月14日 [Default]
いよいよ来年、平成30年より「無期転換ルール」が本格的に始まります。
「本格的に」というのは、通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象だからです。
つまり「来年4月1日以降どうなるか?」ということになります。
ご存じない?!
それは非常にまずい!!
該当する従業員がいる経営者の皆様は確実に理解しておく必要があります。
「無期転換ルール」とは何か?
⇒労働契約法の改正により、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申し込みによって無期労働契約に転換されるルール
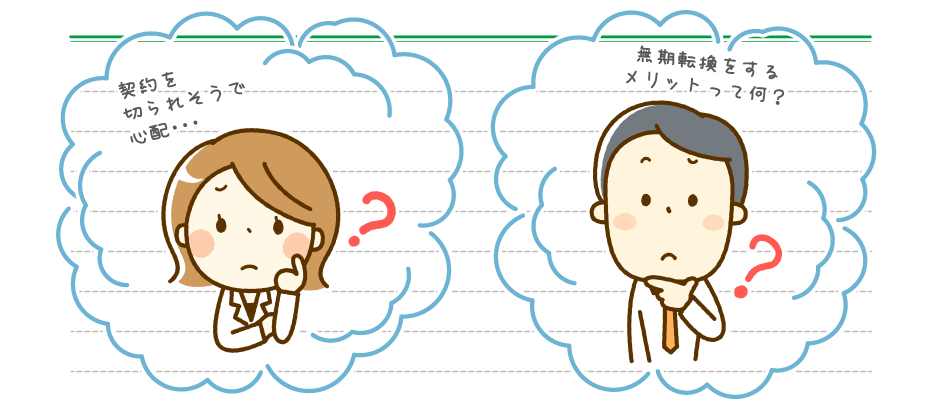
簡単な例を挙げれば、1年契約の契約社員をずっと契約更新を続けた結果、通算5年に達したときに契約社員が「無期契約社員」にしてください」と申し出れば、使用者はその通りにしなければいけないということです。
上記の場合だと、5回目の契約更新の際に「無期転換申込件」が労働者に発生します。
その後1年以内に申し込みがあれば翌年の6回目の契約更新の際には無期労働契約になるわけです。
有期契約労働者を多く抱えている大企業などは大変です。
来年に向けて現在様々な動きが出ています。
それは後述するとして、仮に有期から無期に転換したとしても、労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間等)は、別段の定めがない限り、直前の有期契約の時と同一となります。(個別の契約次第で変更可能)
要は、有期契約だと労働者はいつ契約を打ち切られるか不安な状態が続くため、無期契約にして雇用の安定を図ってくださいということです。
当然、無期雇用というだけで「正社員」ではありません。
さて、前述した「様々な動き」ですが、少し前に報道されたのは東京大学の非正規教職員への今後の対応です。
東京大学では、大学独自のルールで「有期契約の契約上限を5年とする」という「東大ルール」を労働契約法改正より前に施行していました。
当然、このルール通りであれば、契約期間は最長でも5年であり無期転換ルールも適用されないということになります。
更に、その後東大はルールを変更し、「パートタイム教職員の再雇用について、クーリング(空白)期間を3ヶ月から6ヶ月に変更しました。
これ、一番の「抜け道」なのです!!
例えば、1年契約で4年間働きました。
その後、6ヶ月間のクーリング(空白)期間の後、1年間契約社員として働きました。
この場合、クーリング(空白)期間が6ヶ月あると、その前の契約期間、つまり4年間はリセットされてしまうのです!!
東大は、この「抜け道」を利用してあらかじめ3ヶ月だとクーリング(空白)期間にならないから、6ヶ月に変更したわけです。
ある意味東京大学がいち早く対応していたのかもしれません・・・。
更に、つい最近自動車大手も無期転換ルールを避けて「骨抜き」にさせる対応をしていたことが判明しました。
トヨタ、ホンダなどの世界に誇る企業です。
「骨抜き」にする方法は、前述の6ヶ月のクーリング(空白)期間の適用です。
これに対し、厚生労働省は法の趣旨にそぐわないとして実態把握する方向です。
大手企業は多くの期間雇用従業員を採用しています。
自動車大手などは、よく求人誌でも「期間工」などの掲載を見ますよね。
「期間工」は非常に重要な人材なのです。
仮に、この「期間工」を「無期間工」にしてしまったら・・・。
仕事の受注がなくなった際に人が無駄に溢れることになります。
人件費を始め、大きく経営を圧迫することになりかねません。
そもそも「6ヶ月のクーリング(空白)期間」を認めたのは国です。
そこを考慮して経営していくのは、経営者として当然だと考えます。
労働者の事だけを考えて、結果企業経営を圧迫しては元も子もありません。
はっきり言って問題化するのは国の失態ですね。
さて、皆様の会社にこのような契約社員、それも契約期間を反復更新している従業員はいらっしゃいますか?
早めに対応を協議しておく必要があります。
期間契約従業員としては、当然無期契約の方が安定して働ける環境を得られるためありがたい制度なのは分かります。
しかし、やはり労使双方がウィンウィンでなければいけないと私は考えます。
中小企業ですと、仮に対象者がいるとしてもそれほど多くの人数はいないと思われます。
大手のような「抜け道」対応ではなく、話し合いによって解決できる部分が多いと思います。
労使双方が納得する形で有期、無期、正社員登用等への道を探っていっていただければと考えます。
「本格的に」というのは、通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象だからです。
つまり「来年4月1日以降どうなるか?」ということになります。
ご存じない?!
それは非常にまずい!!
該当する従業員がいる経営者の皆様は確実に理解しておく必要があります。
「無期転換ルール」とは何か?
⇒労働契約法の改正により、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申し込みによって無期労働契約に転換されるルール
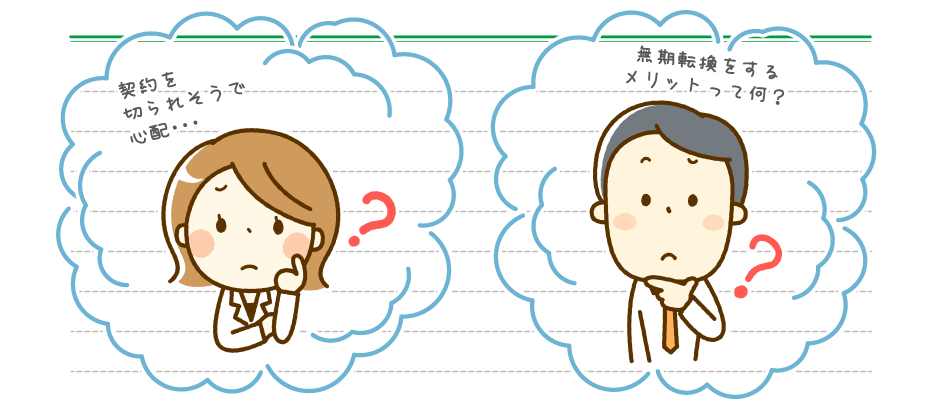
簡単な例を挙げれば、1年契約の契約社員をずっと契約更新を続けた結果、通算5年に達したときに契約社員が「無期契約社員」にしてください」と申し出れば、使用者はその通りにしなければいけないということです。
上記の場合だと、5回目の契約更新の際に「無期転換申込件」が労働者に発生します。
その後1年以内に申し込みがあれば翌年の6回目の契約更新の際には無期労働契約になるわけです。
有期契約労働者を多く抱えている大企業などは大変です。
来年に向けて現在様々な動きが出ています。
それは後述するとして、仮に有期から無期に転換したとしても、労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間等)は、別段の定めがない限り、直前の有期契約の時と同一となります。(個別の契約次第で変更可能)
要は、有期契約だと労働者はいつ契約を打ち切られるか不安な状態が続くため、無期契約にして雇用の安定を図ってくださいということです。
当然、無期雇用というだけで「正社員」ではありません。
さて、前述した「様々な動き」ですが、少し前に報道されたのは東京大学の非正規教職員への今後の対応です。
東京大学では、大学独自のルールで「有期契約の契約上限を5年とする」という「東大ルール」を労働契約法改正より前に施行していました。
当然、このルール通りであれば、契約期間は最長でも5年であり無期転換ルールも適用されないということになります。
更に、その後東大はルールを変更し、「パートタイム教職員の再雇用について、クーリング(空白)期間を3ヶ月から6ヶ月に変更しました。
これ、一番の「抜け道」なのです!!
例えば、1年契約で4年間働きました。
その後、6ヶ月間のクーリング(空白)期間の後、1年間契約社員として働きました。
この場合、クーリング(空白)期間が6ヶ月あると、その前の契約期間、つまり4年間はリセットされてしまうのです!!
東大は、この「抜け道」を利用してあらかじめ3ヶ月だとクーリング(空白)期間にならないから、6ヶ月に変更したわけです。
ある意味東京大学がいち早く対応していたのかもしれません・・・。
更に、つい最近自動車大手も無期転換ルールを避けて「骨抜き」にさせる対応をしていたことが判明しました。
トヨタ、ホンダなどの世界に誇る企業です。
「骨抜き」にする方法は、前述の6ヶ月のクーリング(空白)期間の適用です。
これに対し、厚生労働省は法の趣旨にそぐわないとして実態把握する方向です。
大手企業は多くの期間雇用従業員を採用しています。
自動車大手などは、よく求人誌でも「期間工」などの掲載を見ますよね。
「期間工」は非常に重要な人材なのです。
仮に、この「期間工」を「無期間工」にしてしまったら・・・。
仕事の受注がなくなった際に人が無駄に溢れることになります。
人件費を始め、大きく経営を圧迫することになりかねません。
そもそも「6ヶ月のクーリング(空白)期間」を認めたのは国です。
そこを考慮して経営していくのは、経営者として当然だと考えます。
労働者の事だけを考えて、結果企業経営を圧迫しては元も子もありません。
はっきり言って問題化するのは国の失態ですね。
さて、皆様の会社にこのような契約社員、それも契約期間を反復更新している従業員はいらっしゃいますか?
早めに対応を協議しておく必要があります。
期間契約従業員としては、当然無期契約の方が安定して働ける環境を得られるためありがたい制度なのは分かります。
しかし、やはり労使双方がウィンウィンでなければいけないと私は考えます。
中小企業ですと、仮に対象者がいるとしてもそれほど多くの人数はいないと思われます。
大手のような「抜け道」対応ではなく、話し合いによって解決できる部分が多いと思います。
労使双方が納得する形で有期、無期、正社員登用等への道を探っていっていただければと考えます。