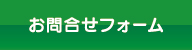2020年12月28日 [Default]
今日で本年の仕事納めとなります。
まだ進めたい仕事もありますがきりがないので納めます!
顧問先のお客様!今年も一年ご愛顧いただき本当にありがとうございました。
関係士業の先生の皆様!今年も色々助けてもらいました!ありがとうございました。
至らない点多々ございますが、来年も一年どうぞ宜しくお願い申し上げます。
振り返ってみれば今年は年明けからコロナでした。もうすぐ1年経ってしまいます・・・。
本当に経営者の皆様も働いている従業員の皆様も大変な一年だったと思います。
個人的にも通常業務で手一杯なところに雇用調整助成金業務が加わったことでかつてない忙しさでした。
しかしこんな状況下で忙しいのに文句なんて言っていられません。ありがたいと思わなければいけません。
会社がどうなるか?雇用をどうすればいいのか?
お客様は本当に本当に神経をすり減らす一年になってしまったことと思います。
来年もこの状況下だとコロナありきの経営を強いられそうです。
でも悲観的になっていても仕方ないとも思います。
みんな同じ状況下です。
当然業種によってはコロナバブルとなっているところもあります。
しかし羨ましがっていても何にもなりません。
今までの基礎・土台を固めるとともに、コロナの影響を少しでも受けないように発想の転換も求められていると思います。

簡単なことではありませんが、こういう時こそできることもあるのかなと考えます。
当事務所はお客様に寄り添って、基礎をしっかりとしながら新しいことを考えるお手伝いをしていこうと強く思っております。
コロナ対応ばかりの話になってしまいましたが、
コロナよりまず皆様の「健康第一」なのは間違いございません。
末筆ではございますが、来年1年の皆様のご多幸を心より祈念しております。
令和2年12月28日
オールウィン社会保険労務士事務所
所長 内山 則仁
まだ進めたい仕事もありますがきりがないので納めます!
顧問先のお客様!今年も一年ご愛顧いただき本当にありがとうございました。
関係士業の先生の皆様!今年も色々助けてもらいました!ありがとうございました。
至らない点多々ございますが、来年も一年どうぞ宜しくお願い申し上げます。
振り返ってみれば今年は年明けからコロナでした。もうすぐ1年経ってしまいます・・・。
本当に経営者の皆様も働いている従業員の皆様も大変な一年だったと思います。
個人的にも通常業務で手一杯なところに雇用調整助成金業務が加わったことでかつてない忙しさでした。
しかしこんな状況下で忙しいのに文句なんて言っていられません。ありがたいと思わなければいけません。
会社がどうなるか?雇用をどうすればいいのか?
お客様は本当に本当に神経をすり減らす一年になってしまったことと思います。
来年もこの状況下だとコロナありきの経営を強いられそうです。
でも悲観的になっていても仕方ないとも思います。
みんな同じ状況下です。
当然業種によってはコロナバブルとなっているところもあります。
しかし羨ましがっていても何にもなりません。
今までの基礎・土台を固めるとともに、コロナの影響を少しでも受けないように発想の転換も求められていると思います。

簡単なことではありませんが、こういう時こそできることもあるのかなと考えます。
当事務所はお客様に寄り添って、基礎をしっかりとしながら新しいことを考えるお手伝いをしていこうと強く思っております。
コロナ対応ばかりの話になってしまいましたが、
コロナよりまず皆様の「健康第一」なのは間違いございません。
末筆ではございますが、来年1年の皆様のご多幸を心より祈念しております。
令和2年12月28日
オールウィン社会保険労務士事務所
所長 内山 則仁
2020年10月30日 [Default]
ブログでも取り上げさせてもらっておりますが、作今重要な判決が立て続けに出ています。
今回も経営者の皆様にとって悩ましい、というかわからない定年時再雇用時の社員の給与をどこまで下げていいか・・・
という問題について注目すべき判決がありましたのでご紹介致します。
今回のケースは、愛知県の自動車学校で起こされていた名古屋地裁の判決になります。
訴えたのは自動車学校の教官の方です。
免許を持っている方ならおおよそ働き方は想像がつくと思います。
この自動車学校に勤めていた男性2名の方ですが、60歳定年後も毎年契約更新をする形で65歳まで勤務したということです。
今は原則希望者全員を65歳まで雇用しなければいけません。
定年時再雇用の一番一般的なケースだと思います。
ここで必ず問題になるのが再雇用時の賃金についてです。
当事務所もたまに再雇用時の賃金をどうすべきか問い合わせいただくことがあります。
非常にグレーなところだと考えております。
明確な線引きがないけれども、他の社員との職務内容や責任の違い、高年齢雇用継続給付や同一労働同一賃金、労働契約法などを総合的に勘案して判断しないと、大きな減額は非常にリスクが高いと思っております。
訴訟を起こした男性2名について、役職は外れたものの定年前と同様の業務を行い、責任も他の社員と同様でした。
ただ賃金については、基本給が定年前から4割から5割程度に減額され、賞与や各種手当も減額または不支給だったとのことです。
この賃金について、不当な賃下げだとして提訴したものです。
判決は注目すべき内容でした。
諸般の事情を勘案して、
「基本給と賞与が定年退職時の60%を下回るのは不合理である」
「労働者の生活保障の観点からも看過しがたく、労働契約法が禁じる労働条件の不合理な違いだ」
ということで、自動車学校に対して差額の支給を命じました。
自動車学校が控訴すれば、また高裁、最高裁で別の判断が出るかもしれません。
しかしながら非常にわかりやすく明示してくれたな、というのが個人的な感想です。
言い換えれば、定年退職前の基本給の60%が最低ラインといえます。
今後自社で定年時再雇用を行う際の一つの判断材料に間違いなくなります。
60%の判断には高年齢雇用継続給付の支給率も影響しているのではないかと考えます。
雇用保険の高年齢雇用継続給付という制度があるのをご存知でしたらおおよそ見当がつくかと思います。
60歳到達時の賃金月額と比して、定年後の賃金月額が大幅に下がった場合に雇用保険の給付を受けることができます。
60歳到達時と比して75%以上の賃金月額があれば対象外です。
しかし、61%超75%未満までは低下率に応じて給付を受けることができます。
61%以下は支給率がMAXとなっています。
ただ、今後はこの60%でも内容を精査すれば不当とすることも当然あり得ます。
60%はあくまでも最低ラインで、75%以上が本当の意味での最低ラインとも解釈できます。
やはり、定年時再雇用時の賃金についても、同一労働同一賃金の考えは避けて通れないでしょう。
しかしながら過去の判決では、一概には言えないが定年時再雇用により賃金が下がるのはやむを得ないという判決もあったと記憶しています。
60歳代はまだまだ元気ですし、今は70歳までの雇用確保に向けて国が動いている最中です。

単純に年齢だけでなく、職務内容、責任の程度等を勘案して慎重に決定していくことが重要です。
また、どうしても大幅な減額が必要なら、商務内容や責任、所定労働時間や労働日数等の労働条件の変更等で補っていくことも一つの方法と考えます。
いずれにしても個別に判断していかないと非常にリスクの高い問題であるといえます。
今回も経営者の皆様にとって悩ましい、というかわからない定年時再雇用時の社員の給与をどこまで下げていいか・・・
という問題について注目すべき判決がありましたのでご紹介致します。
今回のケースは、愛知県の自動車学校で起こされていた名古屋地裁の判決になります。
訴えたのは自動車学校の教官の方です。
免許を持っている方ならおおよそ働き方は想像がつくと思います。
この自動車学校に勤めていた男性2名の方ですが、60歳定年後も毎年契約更新をする形で65歳まで勤務したということです。
今は原則希望者全員を65歳まで雇用しなければいけません。
定年時再雇用の一番一般的なケースだと思います。
ここで必ず問題になるのが再雇用時の賃金についてです。
当事務所もたまに再雇用時の賃金をどうすべきか問い合わせいただくことがあります。
非常にグレーなところだと考えております。
明確な線引きがないけれども、他の社員との職務内容や責任の違い、高年齢雇用継続給付や同一労働同一賃金、労働契約法などを総合的に勘案して判断しないと、大きな減額は非常にリスクが高いと思っております。
訴訟を起こした男性2名について、役職は外れたものの定年前と同様の業務を行い、責任も他の社員と同様でした。
ただ賃金については、基本給が定年前から4割から5割程度に減額され、賞与や各種手当も減額または不支給だったとのことです。
この賃金について、不当な賃下げだとして提訴したものです。
判決は注目すべき内容でした。
諸般の事情を勘案して、
「基本給と賞与が定年退職時の60%を下回るのは不合理である」
「労働者の生活保障の観点からも看過しがたく、労働契約法が禁じる労働条件の不合理な違いだ」
ということで、自動車学校に対して差額の支給を命じました。
自動車学校が控訴すれば、また高裁、最高裁で別の判断が出るかもしれません。
しかしながら非常にわかりやすく明示してくれたな、というのが個人的な感想です。
言い換えれば、定年退職前の基本給の60%が最低ラインといえます。
今後自社で定年時再雇用を行う際の一つの判断材料に間違いなくなります。
60%の判断には高年齢雇用継続給付の支給率も影響しているのではないかと考えます。
雇用保険の高年齢雇用継続給付という制度があるのをご存知でしたらおおよそ見当がつくかと思います。
60歳到達時の賃金月額と比して、定年後の賃金月額が大幅に下がった場合に雇用保険の給付を受けることができます。
60歳到達時と比して75%以上の賃金月額があれば対象外です。
しかし、61%超75%未満までは低下率に応じて給付を受けることができます。
61%以下は支給率がMAXとなっています。
ただ、今後はこの60%でも内容を精査すれば不当とすることも当然あり得ます。
60%はあくまでも最低ラインで、75%以上が本当の意味での最低ラインとも解釈できます。
やはり、定年時再雇用時の賃金についても、同一労働同一賃金の考えは避けて通れないでしょう。
しかしながら過去の判決では、一概には言えないが定年時再雇用により賃金が下がるのはやむを得ないという判決もあったと記憶しています。
60歳代はまだまだ元気ですし、今は70歳までの雇用確保に向けて国が動いている最中です。

単純に年齢だけでなく、職務内容、責任の程度等を勘案して慎重に決定していくことが重要です。
また、どうしても大幅な減額が必要なら、商務内容や責任、所定労働時間や労働日数等の労働条件の変更等で補っていくことも一つの方法と考えます。
いずれにしても個別に判断していかないと非常にリスクの高い問題であるといえます。
2020年10月21日 [Default]
国の政策目標として男性の育休取得率を今より大幅に上げることがあります。
最近は国の後押しからか、今までよりは上がってきている状況です。
でもまだまだ目標には程遠いから更なる政策を!
ということで、厚生労働省の審議会が男性の産休制度を作ろうとしているという情報がありました。
子供の出産直後にとってもらうものです。
現状の産休は産前6週間産後8週間(例外あり)が基本となっております。
子供が生まれた場合、確かに男性としても生まれたばかりのこと一緒に過ごせたら嬉しいですよね。
生まれたばかりの時は賛成できます。

現状でも男性の育休制度は当然認められています。
取得するかしないかは本人の判断になります(義務化の話もあるようですが・・・)。
産休もそうなると思っています・・・。
義務化というのは個人的には??という感じです。
大企業はともかく、中小企業にとっては大きな問題となります。
従業員1,000人規模のうちの1名と従業員10人のうちの1名が取得するのでは全く影響が異なります。
いや10人と言わず、従業員1名の企業だったらもはや他の従業員を採用するしか道がなくなります。
最近の国の政策は、やむを得ないのかもしれませんが中小企業に大きな負担がかかるものばかりです。
政策立案段階でどこまで中小企業のことが考慮されているのか疑問に感じることが多々あります。
有識者会議等で検討するのであれば中小企業の代表者も何人か入っていてほしい。
その点、いつも確実に中小企業の現状を訴えてくれるのは日本商工会議所だと思います。
今回の男性の産休についても「慎重な検討を」と求めたとのことです。
そして「新たな制度を創設するよりも既存の制度(男性の育休等)の認知度を上げて利用を促進していくべきだ」と提言したとのこと。
まったくもって同感です!!
これは余談になりますが、男性社員が育児休業を取っても、あまり育児に参加できない、せっかく育児休業を取得したのに奥さんに家にいることを嫌がられる・・・笑、などよく聞きます。
仮に私がどこかの社員で育児休業をとったら、家にいるのを嫌がられ、怒られ、けんかをし、お互いストレスをためる・・・・
想像しただけで怖いです笑
そして予定より早く職場復帰ですね。
もちろん最近はイクメンが多いのでしょうから私のような男性は少数派なのかもしれません。
いずれにしても生まれてくるお子さんとの大切な時間は限られています。
労使ともにメリットのある制度であれば最高なのは間違いございません。
いろいろな意見を聴きながら議論していただきたいと思いました。
最近は国の後押しからか、今までよりは上がってきている状況です。
でもまだまだ目標には程遠いから更なる政策を!
ということで、厚生労働省の審議会が男性の産休制度を作ろうとしているという情報がありました。
子供の出産直後にとってもらうものです。
現状の産休は産前6週間産後8週間(例外あり)が基本となっております。
子供が生まれた場合、確かに男性としても生まれたばかりのこと一緒に過ごせたら嬉しいですよね。
生まれたばかりの時は賛成できます。

現状でも男性の育休制度は当然認められています。
取得するかしないかは本人の判断になります(義務化の話もあるようですが・・・)。
産休もそうなると思っています・・・。
義務化というのは個人的には??という感じです。
大企業はともかく、中小企業にとっては大きな問題となります。
従業員1,000人規模のうちの1名と従業員10人のうちの1名が取得するのでは全く影響が異なります。
いや10人と言わず、従業員1名の企業だったらもはや他の従業員を採用するしか道がなくなります。
最近の国の政策は、やむを得ないのかもしれませんが中小企業に大きな負担がかかるものばかりです。
政策立案段階でどこまで中小企業のことが考慮されているのか疑問に感じることが多々あります。
有識者会議等で検討するのであれば中小企業の代表者も何人か入っていてほしい。
その点、いつも確実に中小企業の現状を訴えてくれるのは日本商工会議所だと思います。
今回の男性の産休についても「慎重な検討を」と求めたとのことです。
そして「新たな制度を創設するよりも既存の制度(男性の育休等)の認知度を上げて利用を促進していくべきだ」と提言したとのこと。
まったくもって同感です!!
これは余談になりますが、男性社員が育児休業を取っても、あまり育児に参加できない、せっかく育児休業を取得したのに奥さんに家にいることを嫌がられる・・・笑、などよく聞きます。
仮に私がどこかの社員で育児休業をとったら、家にいるのを嫌がられ、怒られ、けんかをし、お互いストレスをためる・・・・
想像しただけで怖いです笑
そして予定より早く職場復帰ですね。
もちろん最近はイクメンが多いのでしょうから私のような男性は少数派なのかもしれません。
いずれにしても生まれてくるお子さんとの大切な時間は限られています。
労使ともにメリットのある制度であれば最高なのは間違いございません。
いろいろな意見を聴きながら議論していただきたいと思いました。