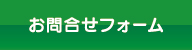平成28年5月11日
平成28年4月より、「キャリアコンサルタント」が新たに国家資格となりました。「キャリアコンサルタント」が行うキャリアコンサルティングによるメリットが生まれる可能性があります。
キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティング(労働者の職業の選択、職業生活設計、職業能力の開発と向上に関する相談に応じ、助言や指導を行うこと)の専門家です。
キャリアコンサルタントが国家資格になることにより、法律によって守秘義務などが課せられるなど、今まで以上に安心して職業に関する相談ができるようになります。
キャリアコンサルタントを使って助成金が受けられる場合もあります。
政府では、企業におけるキャリアコンサルティングの導入支援策として、「セルフ・キャリアドッグ」(労働者のキャリア形成における「気づき」を促すため、定期的にキャリアコンサルティングを受ける機会を設定する仕組み)を推奨しています。
企業でセルフ・キャリアドッグ制度を導入し、実際に行った場合に50万円(大企業は25万円)を支給する助成制度(キャリア形成促進助成金「制度導入コース(セルフ・キャリアドッグ制度」)もできております。
セルフ・キャリアドッグ制度導入で期待される効果としては、下記のものが挙げられます。
・従業員の職場定着や働く意義の再認識の促進
・企業における人材育成上の課題や従業員のキャリアに対する意識の把握など
⇒企業全体の生産性の向上に資する
従業員、特に有能な従業員の職場定着や、若い世代の人材育成、意識改革等はどこの企業でも問題になっていると思います。この機会に助成金を利用して企業経営力のアップを図ることも一案かと存じます。
平成28年5月6日
児童扶養手当の2人目以降の支給額が最大で倍額になります所得の低い「ひとり親」に支給されている児童扶養手当を増額することが決定しました。
2人目以降の支給額が、8月分(12月支給分)から最大で現行の倍になります。
児童扶養手当は現在、1人目の子どもに最大で月42,330円支給されています。
2人目以降は月5,000円、3人目以降は月3,000円ずつに減ります。
今回の決定で2人目以降の支給額を所得に応じて増額することになりました。
例えば、子どもが2人で年収171万7千円未満の世帯なら、2人目は倍の10,000円になります。
平成28年4月20日
平成28年4月1日より、改正障害者雇用促進法が施行となっております。簡単に内容を記載すると以下の通りです。
1・障害者に対する差別の禁止
雇用の分野における障害を理由とする差別的取り扱いを禁止する。
2・合理的配慮の提供義務
事業主に、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることを義務付ける。
ただし、当該措置が事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなる場合を除く。
3・苦情処理・紛争解決援助
事業主に対して、1と2に係るその雇用する障害者からの苦情を自主的に解決することを努力義務化。
1と2に係る紛争について、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の特例を整備
以上、ざっと記載しましたが、要は障害者だということを理由とした差別的取り扱いをしなければよいのです。
例えば、障害者の業務上の職業能力等を適正に評価した結果、通常の労働者より劣った、というような合理的な理由による異なる取り扱いまでを禁じるものではありません。
上記の内容が守られず、必要があると認めるときは、厚生労働大臣から事業主に対し、助言、指導又は勧告が行われます。
ただ、前述しましたが、障害者ということを理由とした差別的取り扱いをせず、障害者でも働きやすい職場づくりを行っていれば問題はございません。
今後も障害者雇用促進法は改正が予定されておりますので、変更があった際には掲示致します。
平成28年4月6日
平成28年4月1日より、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」、通称「女性活躍推進法」が全面施行となりした。この施行に伴い、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主は、行動計画の策定・届出・公表などが必要となります。
該当する事業主は以下の項目が義務化されます。
○自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
○状況把握、課題分析を踏まえての、(1)計画期間、(2)数値目標、(3)取組内容、(4)取組の実施期間を盛り込んだ行動計画の策定と、策定した行動計画について非正社員を含めたすべての労働者への周知と外部への公表
○行動計画を作成した旨の都道府県労働局への届け出
○女性の活躍状況に関する情報の公表
なお、常時雇用する労働者数が300人以下の事業主の方は、上記(1)から(4)は努力義務となっております。
女性活躍推進法に基づき、行動計画を策定し、策定した旨の届け出を行った事業主のうち、一定の基準を満たし、女性の活躍推進に関する状況などが優良な企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定は3段階で、認定を受けた企業は、認定マーク「えるぼし」を商品や広告、名刺、求人票などに使用し、女性の活躍を推進している企業であることをアピールすることができるようになります。
女性の活躍が求められる時代です。
大手企業だけでなく、中小企業でも積極的に女性を採用し、女性の働きやすい職場を作り、登用することで企業価値も上がってくものと思います。
平成28年3月31日
4月よりパワハラや解雇、マタハラやセクハラなどの相談対応を労働局が一元化します4月より、「雇用環境・均等部」が新たに設置されるとのことです。
今までは、パワハラ・解雇と、マタハラ・セクハラは違う部署が相談対応や指導を行っていました。
ただ、昨今の社会情勢で上記のような境界線がはっきりしない問題や重複する問題が出てきたことが原因とのことです。
神奈川労働局が重視するポイントは3点
1・総合的な行政事務の展開
「雇用環境・均等部」が、「女性の活躍促進」や「働き方改革」などの企業・経済団体への働きかけをワンパッケージで効果的に実施
2・労働相談の対応の一体的実施・個別の労働紛争の未然防止と解決の一体的実施
「雇用環境・均等部」が、労働相談の対応を一体的に実施。また、個別の労働紛争を未然に防止する取り組み(企業への指導)と解決への取り組み(調停・あっせんなど)を一体的に実施
3・業務実施団体の整備・強化
女性の活躍促進、ワーク・ライフ・バランスの推進、働き方改革などの取り組みを強力に進めるため、「雇用環境・均等部」に専門官職(雇用環境改善・均等推進指導官)を配置
というようなポイントが挙げられております。
昨今の雇用情勢を鑑みると、新たに設置される「雇用環境・均等部」は非常に重要な部署になるのは間違いないと思います。
私ども社会保険労務士としても、様々な情報提供等期待したいと思います。
平成28年2月23日
平成28年度の雇用保険料率は引き下げられ一般の事業なら1000分の11になります。平成28年4月1日からの雇用保険料率は一般の事業は1000分の13.5から1000分の11に引き下げられます。
雇用情勢が改善し、失業等給付にかかる積立金残高が6兆円を超えるなど安定していることが要因です。
農林水産及び清酒製造の事業は1000分の15.5から1000分の13に引き下げ。
建設の事業は1000分の16.5から1000分の14に引き下げ。
会社負担分と従業員負担分の内訳は当ホームページ内の「お役立ち情報」をご参照ください。
また、平成28年4月1日からの給与計算もご注意ください。
平成28年2月22日
平成28年4月より、傷病手当金と出産手当金の計算方法が変更になります傷病手当金と出産手当金の計算方法について、
平成28年4月より、支給開始される前1年間の給与を基に計算された金額で支給されます。
平成28年3月まで
1日当たり金額 {休んだ日時点の標準報酬月額}÷30日×2/3
平成28年4月以降
1日当たり金額 {支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額}÷30日×2/3
なお、傷病手当金と出産手当金の併給について
今までは、出産手当金を受給する場合、その期間については傷病手当金を受給できませんでしたが、
平成28年4月からは、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多い場合、その差額を受給できます。
平成28年2月18日
健康保険の標準報酬月額の上限改定及び累計標準賞与額の上限変更
平成28年4月より以下の2点が変更になりますのでご注意ください。
1・健康保険標準報酬月額上限改定
現在の標準報酬月額の上限は月額表でいうと第47級の報酬月額1,175,000円以上の1,210,000円が最高等級となっております。
平成28年4月よりその上に更に3等級増えることになりました。
具体的には以下の通りです。
第48級 標準報酬月額1,270,000円 (1,235,000円以上1,295,000円未満)
第49級 標準報酬月額1,330,000円 (1,295,000円以上1,355,000円未満)
第50級 標準報酬月額1,390,000円 (1,355,000円以上)
となります。
この改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者の方には、事業主に対して平成28年4月中に管轄の年金事務所より「標準報酬改定通知書」が送付されます。
月額変更届の提出の必要はございません。
改定後の保険料は4月分(5月納付分)より適用となりますので給与計算の際にはご注意ください。
2・累計標準賞与額の上限の変更
現在の健康保険法で定める年度の累計標準賞与額の上限は540万円となっております。
平成28年4月より、この年度の累計標準賞与額が573万円に引き上げられます。
賞与額が年間で500万円を超える方、特に役員報酬が出る会社は注意が必要です。
いずれも高所得者対策と考えられますが、まだ序の口だと思います。
今後は厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定等も出てくると考えられます。
平成28年2月17日
平成28年3月より協会けんぽの全国の健康保険料率が変更になります。全体的に健康保険料率は下がるようです。
介護保険料率に変更はございません。
給与計算の際に健康保険料率の変更を忘れないようご注意ください。
<給与計算上の注意>
3月分より改定となるということは、通常の翌月徴収の会社様ですと、3月分(4月支給分給与)から変更になります。
3月分からだから3月支給の給与計算から変更してしまうお客様がよくいらっしゃいます。
今からチェックしておいてください。
全国の健康保険料率は、
下記、全国健康保険協会URLをご参照ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h28/280203
平成28年1月15日
一昨日の新聞朝刊の一面にて「社会保険に加入すべきなのに加入していない未加入事業所が全国で79万社」「厚生年金保険に加入資格があるのに国民年金に加入している従業員が全国で200万人」「今年から厚生労働省は、関係省庁と緊密に連携を取って、未加入事業所の指導、調査、加入勧告を徹底的に行っていく」と報道されておりました。現在社会保険未加入の事業所の経営者の皆様、当事務所にお気軽にご連絡ください。
真摯に今後の方向性をアドバイスさせていただきます。